JCSS(ISO 17025)の品質マニュアルの作り方 第5章 前半
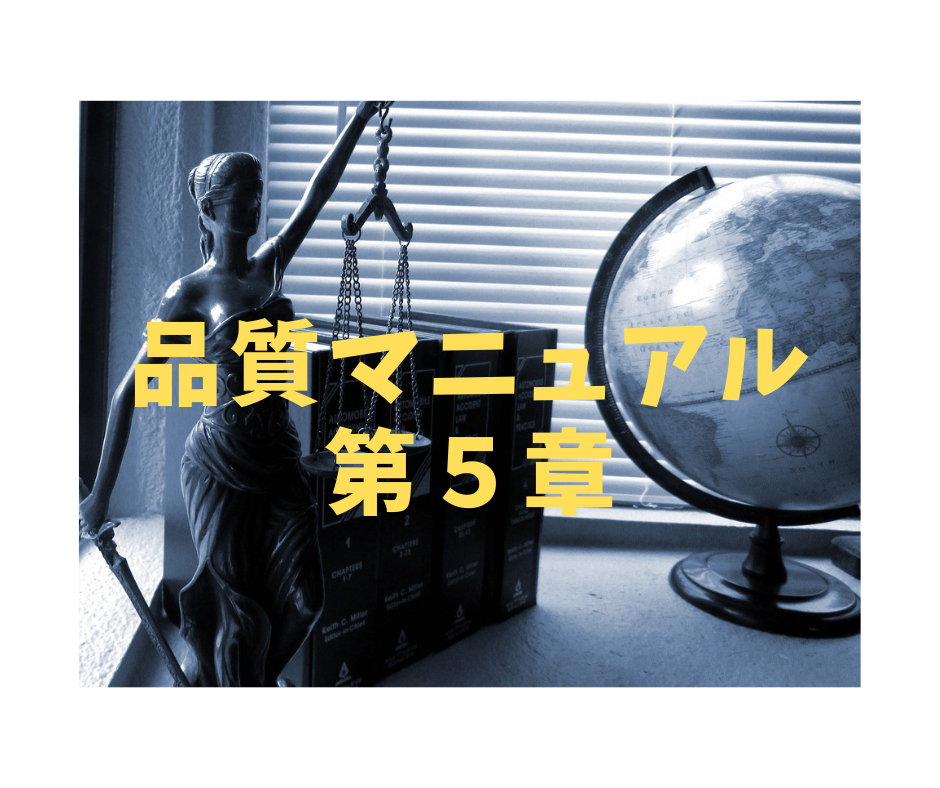
品質マニュアル第5章は組織についてです。今回の記事では5章の前半の書き方を解説します。
5.1 校正機関
この項目では校正機関の定義をします。どの会社のどの部署がどんな校正活動をするか定義します。
5.2 管理主体
試験所・校正機関は総合的な責任をもつ管理主体を持たなければならない
ISO 17025 5.2
原文では”トップマネジメント”となっていましたが、”ラボラトリマネジメント”となりました。これは一段階現場に近いラボラトリを実質管理する存在です。
今までは社長やCEOが管理主体として必要でしたが、より現実的に事業所長や工場長が管理主体になれるようになりました。
管理主体では、最高責任者、品質管理者、技術管理者、校正担当者を上げ、それぞれの役割を定義します。それぞれ次のような仕事があります。
最高責任者
- 校正機関活動に関する最高責任を持つ
- 品質管理者の任命を行う
- 校正証明書の発行権限を持つ
- 改善業務を推進する
品質管理者
- マネジメントシステムの実施、維持及び改善
- マネジメントシステムからの逸脱、実施手順からの逸脱の特定
- 逸脱を防止又は最小化する処置の開始
- 管理主体へのマネジメントシステムの実施状況、改善の必要性に関する報告
- 試験所校正機関活動の有効性の確保
- 校正業務に関する記録
技術管理者
- 校正業務において決められた技術水準を維持する責任を持つ
- 校正業務に使用する設備の管理を行う
- 教育訓練を行う
校正担当者
- 校正試験を実施する
技術管理者はISOの規定では必ず必要ではないですが、品質管理者と一緒にすると監査の時につらいです。(2005年版の)監査では品質分野と技術分野を同時進行する場合があり、それぞれに対応できる責任者がいた方が良いです。
5.3 活動の範囲
活動の範囲では試験所のスコープを書きます。ここでは「試験所の業務は以下の範囲とする」として、以下に認定範囲を書きます。まだ認定されていない事業者はNITEのHPで認定事業者検索をして自分たちと同じ認定範囲の事業者を参考にしてください。
5.4 施設の場所
ISO 17025の5.4章では、試験所は~の要求事項を満足するように実施する、と書かれていますが、ここでは校正を実施する住所を書いておきます。移動校正車などがあればそれのことも書いておきます。
まとめ
5章は長いので後半は別の記事に書き直します。品質マニュアルまだまだ長いですが、全部記事にできるかどうか?頑張ります。
